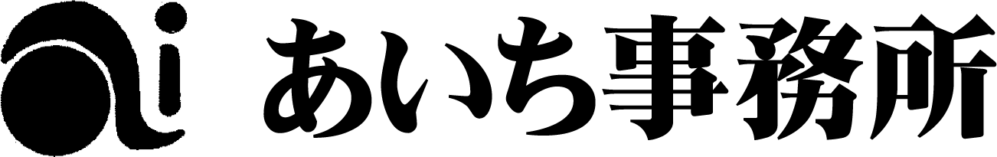法に溺れてまで・・・・信託と調査士
法に溺れてまで・・・・信託と調査士
私見です。自分は民事信託を活用する者ではありません。
平成19年、2007年から、家族・民事信託が施行され、18年経ちました。
以来、信託銀行にほぼ限られていた商事信託との併存にて、新しいスタイルの家族間財産解決法として、当初歓迎されましたが・・・
私見ながら、今後も汎用性は広がらないでしょう。
先輩調査士さんから質問をいただきました。
新築した建物の表題登記の「受託者」を表題部所有者として申請してもらいたいと依頼を受けたが、法務局に尋ねても、けんもほろろ。
会員間で、経験者は?
なかなか、いないでしょうね。確かに、調べてみると、真の資金出資者=所有者=「委託者」との信託契約が成立してさえすれば、表題登記は受託者からすることが出来るとされています。
しかし、司法書士サイドが、保存登記時点で連件で信託登記を必ず申請することで、信託原簿において、法律関係がはっきり公示されるから、受託者の表題登記をそのまま土地家屋調査士は「黙って」申請すれば良いというものではありません。
93条調査報告書には、どう記しますか?
所有権証明書として確認済証を覗くと、そこには、受託者の名が記載されているケースもあるようです。だったら、所有者は受託者で問題ないのでは?・・ではありませんね。
土地家屋調査士は、原始取得者としての委託者、建物を建てる発注した方を所有者として認定しなければなりません。
設計事務所は、言われるがまま、委託者の資金を投じて建築する建物の建築確認申請書の所有者欄に受託者の名前を記した…それを批難しても仕方ありません。
もう一度、93条に記すべきは、真の所有者は誰かという事に尽きますと。
司法書士に言われたから…では、何の根拠にもなりません。そこをしっかり踏みとどまっていただいて、真の所有者と、現在、委任状に印鑑を押そうとする受託者との関係を、A4 1枚に、正しい所有権証明書として作文すべきです。
そこに、委託者、受託者双方に、今回の申請人の特定の理由を、土地家屋調査士として明記すべきです。
しかし、委託者は建物の完成時に、既に認知状態となっている事もあります。(本来は、その時点で成年後見申立がなされる事が遵法ですが…)であれば、土地家屋調査士としてその経緯を、受託者の自己申述書として、A4 1枚に作成しましょう。勿論、93条のうしろに、公正証書の信託契約書もフルに参考添付します。
そして、最も大切なのは、例え93条を書き上げ、表題登記が申請され、①保存、信託登記の申請がなされなかった場合、②表題、保存、信託登記が登記完了後に、信託錯誤抹消された場合・・・
→ ①②共に、表題部の受託者登記名義人の名が残ってしまいます。
相続等を経て、信託関係家族が居なくなると、全く、建物所有者の真実は、登記記録だけではわからなくなります。
かつて埼玉法務局で、①、②を理由に「受託者による表題登記」を受理出来ないとした例もあったとの事。
そこへ、令和6年(2024年)1月10日民事二第17号によって、受託者単独申請が簡便化される先例が出され、(私見ながら)信託を汎用する方向性で中間省略登記=免許税の節税が可能となりました。 クダラン・・・(私見です)
家族間で信頼出来ない人物がいるから、限定的な家族内の断絶対抗策。
→ 弁護士、司法書士は信託におぼれる事なかれ!
→ 土地家屋調査士は、巻き込まれることなく、基本通り、真の所有者探索を!
他士業者に、負けないこと!!